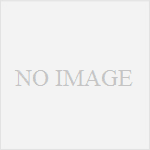なぜオタクは保守的なのか?

最近「ジェンダー×小説ガイドブック 日本近現代文学の読み方」という本を読んだということもあり、以前から疑問に思っていたことを改めて考える機会を得た気がします。
先にその疑問は何かということを述べると、見出しにもあるように「なぜオタクは保守的なのか?」ということです。
オタク文化は別の言い方をすれば「サブカルチャー」と言われるように、いわゆるメインストリームとなる一般向けに作られたコンテンツとは異なる、言ってみれば「限られた人にだけ深く刺さる」ものとして存在しています。
結果的にサブカルチャーとして作られたものが一般向けにも受けて大きなヒットになることはあるものの、基本的には「メジャーではないもの」として扱われることが多いと言えます。異論があるかもしれませんが、私自身の認識がそうであるという前提としてひとまず受け入れてください。
一般向けとして作られる商業作品は当然ながらより多くの人に受け入れられることを目的に作られますので、必然的に多数決で数の大きい方の価値観が採用されます。
対してサブカルチャーは(少なくとも表向きは)一般受けよりも数少ない愛好家を意識した制作となるので、価値観としては多数決ではないマイナーな価値観による独特なものが下敷きになるはずではないかと思うわけです。
しかし「オタク向け」として作られるコンテンツの多くは非常に保守的な価値観―ーー場合によっては前時代的と言えるような―ー―ものに沿っていることも珍しくなく、価値観そのものに対して疑問を投げかけるような作品はむしろ好まれない傾向すら伺えたりします。
具体的な例として最も顕著なのが「結婚」に関わるもので、入籍することに非常に特別な価値観を付与しているケースが多く見られます。
BLやGL、あるいは異種族間の恋愛など世間一般的にメジャーな【異性間の恋愛・結婚】とは異なる人間関係や恋愛模様を題材に取り扱っているような場合であっても、その恋愛のゴールが「入籍」など法律婚と設定されていたり、その際にどちらかの姓に統一する「家制度」を喜んで受け入れていたりします。
選択的夫婦別姓や同性婚の問題は現実的には非常にセンシティブな政治的意見が二分される問題ですが、コンテンツ的にメジャーではないものを好むかのように思われる「オタク」たちの方がむしろそれらの旧習を全く疑問を持たずに受け入れているというのは非常に不思議です。
それまでの体制的な価値観を覆すような新しい文化が前衛的な創作物から発生するという例は近現代においては決して珍しいことではありませんが、オタク文化というのはそうした従来の価値観に疑問を持つ人が創作という形で表現をするという方向には向いていないと言っても決して過言ではないでしょう。
BLにおける「攻」と「受」での役割固定


もう一つ最近読んだ本として「BL研究者によるジェンダー批評入門」と「BL進化論」(いずれも溝口彰子著)があります。
こちらはBLという創作文化を細かく分析した内容となっておりますが、その傾向として男性同士の恋愛という男女にはない対等な関係を描いているようで、実際には古い男女の役割を二人のいずれかに付与して関係を成り立たせていると指摘されています。
いわゆる「攻」と「受」と言われるものですが、「攻」にあたる(セックスをする場合に「挿れる」側)タイプでよくあるのが【現実離れした経済力】【高身長の美形で女性から非常にモテる】【社会的地位の高い仕事をしている】と言ったことが挙げられます。
反対に「受」(同「挿れられる」側)によくあるタイプが【平凡な容姿】【低収入もしくは生活に困窮している】【女性と間違えられることがよくある中性的な雰囲気】などがあります。
もっともこれらの分類は90年代くらいに起こったBLブームの頃からあるものなので、最先端のBL作品ではあえてそれらの型を壊して意外性を狙ったものも見られてはいます。
しかしながら小手先の形は変わっていても、「攻」と「受」の客観的な立場や見た目には王道と言われるパターンがあると言ってもいいでしょう。
一方でそれらの役割分担で近代的なジェンダーと異なるのが、「攻」側が仕事だけでなく料理など家事を完璧にこなすような場合で、何かと自分に自信がなかったり卑屈な思考をしがちな「受」を何が何でも受け入れて世話を焼くというのもBLにありがちな形です。
以前から言われていることではありますが、BLコンテンツを作っているのは作者から編集者、読者に至るまでほぼ全て女性であることから、一見男性同士の関係を描いているかのように見えて実際には女性である自分の代理としての「夢」を投影しているというのもまたこの界隈です。
詳しくは前述の書籍を参照してもらいたいですが、その自己投影も単純なものではなく男性同士にその行為をさせるというところにワンクッションがあるという複雑さもあります。
私個人として気になるのはむしろそうした投影の方法よりも、その恋愛としての成就が非常に保守的なところにとどまっているというところです。
高価なおそろいの指輪をプレゼントする、擬似的もしくは何らかの形で結婚をする、家庭内での役割分担を主従はっきりさせる、などなど人気のBL作品を見てみると男女の恋愛そのままもしくは前時代的な「形」に収まることがゴールとして設定されていることがよくあります。
一方でGL、いわゆる「百合」ものはどうかということですが、指輪や同姓になることを考えるシチュエーションなど恋愛の成就としてのゴールを擬似的な「結婚」を意識していることはBLとはそれほど変わらないものの、大きな差と言えるのがその作品のほとんどが高校生くらいまでの10代で終わるようにできているという点です。
ここ最近になって「社会人百合」と言われるような20代以上の女性が登場してくるものもポツポツと出てきていますが、それでも全体から見ればイレギュラーな存在にとどまっておりBL作品に比べて年齢の頒布図が非常に狭い範囲に収まっているのは大きな特徴と言えます。
この現実的な婚姻適齢以前までの恋愛関係を描くということ自体が非常に古い価値観によるもので、「将来的には異性愛に【戻って】男性と家庭を築く」ことを暗示しており、BL以上に保守的な価値観のまま作品づくりがされていると言ってもよいでしょう。
もう一つ付け加えれば、BLものにおいては「攻」「受」の役割が固定化されているのが一般的であるのに対し、GLではそれほど綿密に「攻」「受」が決められていないことも多いです。
BL用語で言うところの「リバ」(攻め受けが交代することがあるカップリングのこと)が標準になっていたりするわけですが、これは決してBLにおける役割固定のようなジェンダー意識から抜け出した価値観で作られているわけではなく、作中に存在していたりいなかったりする「男性」からの視線が存在しているがゆえのことと言えるでしょう。
平たく言えば一見女子高生同士の恋愛を描いているもののように見えて、実際にはそれは読者である「男」が性的に鑑賞して楽しむために二人だけで関係が完結しないように意識して作られているということです。
BLにしてもGLにしても、一見LGBT+のような比較的新しい性の価値観を描いているかのようで、内容はむしろ旧来の価値観を踏襲し社会秩序を乱さない安心安全な範囲を踏み越えないように注意をして枠組みが作られているとまとめても決して暴論ではないと思います。
「これはただの同性愛ものではない」という言葉の裏にあるもの
前述した書籍「BL進化論」および「BL研究者によるジェンダー批評入門」に繰り返し説明されている言説として、「ただの同性愛ものではない」という言い方への批判があります。
同性愛を描いた作品について、「これは単なる同性愛の物語ではなく、普遍的な物語です」みたいなコピーをつけたりするの、本当に私は禁止したいんです。ずーっと蔓延していますよね。
BL研究者によるジェンダー批評入門: 言葉にならない「モヤモヤ」を言葉で語る「ワクワク」に変える、表象分析のレッスン P.241
同じようなものにBL、GLいずれの作品にも非常によく登場する「お前・あなたを好きになったのは同性だからじゃなく、人間を好きになった」という言い訳じみたセリフがあります。
この手の言葉にはいくつかバリエーションがあり、直接的に「ホモ(レズ)じゃない」と言うこともあれば、初期の葛藤の一部として自分は同性愛者じゃないはずなのにどうしてこんなにドキドキするんだろう、といった感情を表現することがあったりします。
※話が脇道にそれますが、GLものではなく一般向けの作品の中にも美人で仕事ができる大人の女性がいつまでも結婚しないというときに「もしかして女が好きなのかな?」というようなからかいをする場面もわりとよくありますね。言われた本人は実は周囲に理解してもらえないような特殊な趣味があったり、表には出せないコンプレックスや秘密があったりというのがオチなのですが、結婚しない理由を「レズ(ホモ)」と疑われることを侮辱的な表現としてて否定的に扱うという点では共通しています。
話を戻して「ただの同性愛ものではない」という言葉についてもう少しツッコミますと、その表現の裏には「ただの同性愛ものは異性愛を扱った物語よりも劣っている」という認識があるわけです。
これも前述の本の内容からの受け売りになりますが「同性愛を描いただけでなく普遍的な愛の物語である」みたいな言い方も「普遍的な愛=異性愛」という前提があっての言葉であるわけで、あたかも同性愛というのは「色欲」の部分にのみにフォーカスされただけのもので本来の恋愛感情ではなく、異性愛こそが心身一体になれる本当の恋愛であるかのように言いたげです。
これは前述した「同性だからじゃなくあなただから好きになった」というセリフから察せられるような、現実的な損得のない真実の愛として同性愛関係を描いていることと一見矛盾をしているようですが、逆に一歩引いて見れば【普通の恋愛】ではない間違った恋愛感情を持っているという罪悪感を創作物として面白おかしく取り上げているというふうに見れば指している方向は同じとも言えます。
※もっとも「単なる~ではない」系の言い方に関しては「単なる恋愛ものではない素晴らしい物語」とか「単なるギャグマンガではなく~」とかいうようなコピーがつけられることがありますので、一般の意識として物語のジャンルの中に自然にヒエラルキーのようなものが存在しているのだろうということだと思います。その場合の最上位ってなんですかね。推理ものとかサスペンスとか、伏線やどんでん返しが含まれる「頭良さそう」な話は「単なる~」って言われないような気がするのでそういうのが創作物としてより高級感があるものなんでしょうか。
さてその「単なる同性愛もの」という言葉に代表される無意識の差別意識の表出についてですが、それはやはり前項で説明したような「擬似的な結婚をゴールに設定した物語設計」が関係しているのではないかと思います。
最近はそうでもなくなってきているようですが、80~90年代くらいまでの同性愛ものの物語というのは最終的に破滅することが前提とされているのが一般的で一つの様式美でもありました。
完全な同性愛が主題の作品ではありませんが、女性同士の友情以上の感情を描いた名作映画「テルマ&ルイーズ」(1991年)のラストシーンにおけるキスからのダイブなどが象徴的で、同性愛は一時的な気の迷いによる熱狂でありそれが過ぎ去ったら【きちんとした異性愛】の世界に戻るか、そうでなければ死ねというのが社会的には安心安全な価値観として存在していたわけです。
「ただの同性愛ものではない」という言葉の背景にあるのがそうした破滅を前提とした同性愛主題作品のテンプレートで、同性愛者がただ愛し合ってセックスをして将来晩年まで過ごす関係を作ることを描くようなものは一般的には面白くない一段下の創作物として扱われてしまう理由です。
従って本来サブカルチャーである同性愛の創作物をメインストリームでも商業的成功させられるレベルにするには「ただの同性愛ものではない」という価値観と付与する必要があり、そのための手段として最終的に破滅的な悲恋にするか、非常に凝った仕掛けでサスペンス的な仕掛けを組み込むか、何か恋愛以外の部分でエモーショナルな感動的な演出をするかという努力が必要になってきます。
私の大好きな映画の一つに「Bound」(1996年)がありますが、こちらは女性同性愛を扱いつつ、サスペンス要素や演出が優秀であり、さらには同性間の恋愛がハッピーエンドを迎えるという点でそれまで見てきた同性愛を扱った映画の価値観を大きく覆すものでした。
こちらの映画はご存じの方も多いと思いますがその後「マトリックス」シリーズを手掛けることになるウォシャウスキー姉妹による作品ですので、やはりLGBT当事者から見て「ただの同性愛ものではない」という価値観への違和感は持たれていたんだなあと思います。
これから増えてほしい「ただの同性愛もの」
私自身がWebの片隅でコツコツと百合ものの創作物を描き続けている身でありますので、こうした創作物に対する社会的な視線は非常に関心のあるところです。
その一方でメジャーな価値観を前提に社会的に安心安全な範囲でしか作られないものに対しての抵抗感も強く感じています。
もちろん創作物全てが政治的なメッセージを持たなくてはならないなんてことはありませんし、日々の生活に疲れている一般の人にとっては旧来からの価値観が揺らがない硬いベースの上の作品の方が好ましいという気持ちもわかります。
ただ個人的には同性愛というテーマを扱いながら、結局は家父長制や異性間での「ロマンティック・ラブ・イデオロギー(人為的に作られた恋愛・結婚・セックスを一体不可分のものとする考え)」に帰結するようなものばかりが量産されるのも面白くないなあと一読者としても思うわけです。
一方で近年欧米映画や映像作品で量産傾向にある「ポリコレ」に過剰に配慮した作品もまた、見ていてつまらないと思うことがよくあります。
それら「ポリコレ」的作品の多くはLGBT+の他にも有色人種や身体障害者などを主要な登場人物にわざとらしく置換していることで、そこに内包する差別や白人・異性愛至上主義に対峙したマイノリティとしての葛藤やアイデンティティをないものとしており、それが作品全体の違和感や矛盾につながっていくのではないかと思います。
メインストリームとしてすでに存在している物語の基盤というのはあくまでも白人であったり異性愛であったりロマンティック・ラブ・イデオロギーであったりする時に共有している価値観をベースに作られているのですから、登場人物だけを単純に別の属性の人物に置き換えてもしっくりとはまるわけがありません。
※追記:この違和感をわかりやすく表現すると、例えば海外の学園ドラマを日本で放映するために登場人物の名称を全員日本風の名前に翻訳したものを見せられている、ということになるのではと思います。「スティーブ」とか「メアリー」とかが全部「祥太朗」とか「若菜」とかに置き換えられてるような感じです。または「キャプテン翼」がサッカーから強引にクリケット競技に置き換えられたものを見せられているような感じと言えばいいでしょうか。
何らかの形で創作をしたことがある人ならばわかると思いますが、例えばベタベタの王道展開をする少女漫画の物語があったとして、その登場人物をそのまま男同士・女同士に置き換えてそのままの話を進めようとしてもどこかしっくりこないというか、面白みがないものになってしまいます。
それこそ「ただの同性愛ものではない」メジャーな価値観にも受け入れられるはずの素敵なストーリーのまま進めているはずなのに、登場人物の属性が差し替わっただけで話そのものがつまらないもののように思えてしまうのです。
なぜか?
それは当然のことで、「ただの同性愛もの」を描いていないからです。
「ただの同性愛もの」というのは、同性間だからこそ感じる―ー―異性愛とは共通しない全く別の種類のーーー恋愛感情をもとにした物語であり、そこにサスペンスやミステリーなど驚くような仕掛けが含まれていたとしても同性間の恋愛要素が主題として損なわれることのない創作物です。
そこに登場する同性愛者が必ずしも現実的でリアルすぎる悲観を持っている必要はなく、物語の一部として同性愛だからこそ発生する気持ちや行動原理が機能しているというのが理想と言えるかもしれません。
※2000年くらいを境目に、実際のゲイや男性の目から見てBLという創作ジャンルが男性を過度に性的なものとして人格を軽視して扱っているのではないかという批判がされるようになってきたせいか、BL作品の中に現実の苦悩や差別を盛り込んだ作品も登場するようになってきました。賛否はあると思いますが、私個人としてはその懊悩があまりに悲観的であったり卑屈なものでありすぎる場合も多く見ていて気分が落ち込むものもあるため、(特にLGBT+当事者ではない人の作る)同性愛を主題にした現実に寄せた作品を手放しに褒めることができなかったりします。
私は思うのですが異性愛としての恋愛の形も決して哲学的な意味で「普遍的」なものではなく、私達が生まれてから自然に目にしながら成長していく創作物のベースを勝手に一般的なものと思い込んでいるだけなのではないでしょうか。
「普遍的」という言葉が適切でなければ、「世の中にある創作物を楽しむための基礎的な素養」とでも言うのでしょうか。
その「素養」が過度に商業的になり創作物における政治的なメッセージがストレスであると嫌われるようになったことで、マイノリティ的な意識や思考を表現する機会が損なわれてしまっているのでは?というのが今の私の考えです。
前にも引用しましたが、非常に素晴らしい言葉だと思ったものを最後にここにも付け加えてこの文章を終わりにしようと思います。
いつか私も「まだ語られていない『女性』」を語ることができるような創作をしてみたいものです。
それが本当のところはいったいなんであるのかがついぞわからない仕組みになっている一度きりの「生」や「死」とおなじように、まだ誰にも知られていない「女性」があるはず。まだ語られていない「女性」があるはず。そして、言葉や物語が掬ってこなかった/こられなかった、声を発することもできずに生きている/生きてきた「女性」がいる。そしてそれらは同時に、「語られることのなかった、女性以外のものやできごと」を照らします。
川上未映子氏が責任編集を勤めた雑誌「早稲田文学」の増刊「女性号(2017・9)」の巻頭挨拶より。