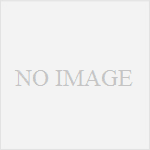今回は読書感想文を書くにあたり、本の内容で特に気になったところを先にまとめておきます。

こちらの「ジェンダー×小説 ガイドブック—日本近現代文学の読み方は近代からの文学作品を中心に、現代のアニメや漫画、映画における女性像について多面的に考察をする非常に良書ですので、ぜひとも興味のある方たちには手にとってもらいたいです。
個人的なおすすめポイントを以下に簡単にまとめていきます。
1.文學界におけるいわゆる「女流作家」というのは「女性の代表的意見」を述べる存在ではないということ。
明治以降の文學界では、物書きという職業を男性のものとする運動が起こった。
これは職業を持つということ自体が男性のみに許されたことにされてきたためであり、男性特有の悩みやライフスタイルを語るものに特化した作品が評価されるようになった。
女流作家もいたが、その読者として想定していたのは女性ではなく男性であり、男性の目を意識した作品が評価されてきた。
そもそもものを書いて収入を得ることができる女性は当時の一般的な女性を全く代表する存在ではなかった。
その転換が起こったのが1970年代ころになるが、それでも女性が女性を描く像は決まった形があるわけではなく、また女性読者のみに閉じられた文章もよしとはされなかった。
※孫引きになって申し訳ありませんが、素晴らしい文章が書籍内で紹介されていましたのでそちらを引用します。
それが本当のところはいったいなんであるのかがついぞわからない仕組みになっている一度きりの「生」や「死」とおなじように、まだ誰にも知られていない「女性」があるはず。まだ語られていない「女性」があるはず。そして、言葉や物語が掬ってこなかった/こられなかった、声を発することもできずに生きている/生きてきた「女性」がいる。そしてそれらは同時に、「語られることのなかった、女性以外のものやできごと」を照らします。
川上未映子氏が責任編集を勤めた雑誌「早稲田文学」の増刊「女性号(2017・9)」の巻頭挨拶より。
2.恋愛=結婚という概念は国家体制への異見から
日本において恋愛・結婚・セックスを一体のものとして扱うようになったのは、北村透谷(1868―1894)の影響が大きい。
それまでは娼館などを利用した「色」と、家の存続を前提にした「婚姻」は別のものとして扱われてきたが、男性作家の手により旧習を批判し個人を確立するものとして恋愛と結婚とセックスを一体化させた「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」というものが人為的に作られた。
これは男性にとっては一つの政治的なメッセージであったが、当時の女性はそもそも自律的な行動が許されていなかったことから「恋愛」そのものが自己を模索する数少ない分野として出来上がることになった。
また男性にとっては同じ女性を間に挟んで男性同士で価値を共有することが一つの絆になっていたのに対し、女性はその媒介役でしかなく実際には「恋愛」といっても男女が対等に描かれるものではなかった。
そのため女性が恋愛に主体的になる物語は決まって破滅することが当然になっており、社会秩序を乱す存在として描かれるようになった。
いわゆる家に入って家庭を守る「まともな女」と、主体的な意思を持って行動する「そうでない女」という全く別の女性像が確立されていく。
3.不可視化された女性同性愛
女性同士の恋愛を扱った物語は昔から存在していた。
しかしそれらは一時的なものであり、いずれは異性愛に落ち着くという前提のもとで描かれるものであり、実際のところ「女性同性愛」の成人女性はいないものであるかのように長らく描かれてきた。
同時に父親との近親相姦的な物語も存在しており、それは発表当初は家父長制など家族制度へのアンチテーゼなど価値観の変容を図る目的で描かれていたのだが、それらは(なぜか)時代の流れとともに反逆的な意味は失われてポルノの一分野として現代まで残されてしまった。
女性同性愛も旧習への批判という意味があるが、「実際には存在しないもの」にされることで間に男性を介したり男性との恋愛をする前の準備のようにした作品が多くなった。「レズビアン」という言葉とともに家父長制に従わないライフスタイルとして存在が認められてきたのはつい最近のことである。
4.差別問題の難しさと多面性
女性はいわば「被差別」側にあたるが、その問題を訴える時の難しさもまたある。
かつて久志富佐子氏が「滅びゆく琉球女の手記」(1932)を発表し、沖縄の人々の経済的困窮や島に取り残された女性の苦境を発表したときに、その内容で引き合いに出した文章に触れて学生代表が「アイヌ人や朝鮮人と同一視されては迷惑する」と発言したことでさらに反論をしたという事件があった。
これによりジェンダー方面と帝国主義的方面の両方から批判される流れとなり結局久志氏は以降作品を発表することがなくなった。
他に気になったところなど
他にも「生む性」として命がけで子供を守る役割を担わせられる物語は多いが、その時に命をかけて守る子供はなぜかほぼ全て男児であるということや、いわゆる「介護」の問題としてジブリ作品に出てくる女性は必ずといってよいほど介護・補助の任務についているという考察などがあります。
思ったのが「女流作家」や「女性文学」といったもの(いわゆる「百合もの」なども含む)であってもそこに描かれる女性像はなぜか一つのテンプレートに収まっており、暗黙の了解のような形をとっているという怖さがあるということです。
それと同じ女性作者でも女性に対するスタンスは一つではなく、非体制的であるかと思えば非常に体制的になっていたりと主張にブレがあったりもするんですね。
そういったところも含め、男性中心の文学史に比べて女性作者や女性の生き方を扱った作品を歴史的にまとめて編纂することの難しさを強く感じました。