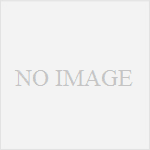日本における一夫多妻制とその消滅

今回も読書感想文です。
【妾と愛人のフェミニズム-近・現代の一夫一婦の裏面史】石島亜由美著 青弓社 (2023/3/27)という書籍ですが、こちらはタイトルの通り日本における「妾」と「愛人」の歴史を取り扱った内容となっています。
「え!?愛人?嫌だな」と思った人もいるかもしれませんが、こちらの書籍ではそうしたなんとなくタブーにされてきた妾・愛人という結婚外の関係を結んだ女性について、非常に綿密に—ある意味では執拗に—まとめてあり、かなり面白く読めます。
まず一つ個人的に読んで驚いたのが、日本において一時的ですが「一夫多妻制」が法的に存在していたということでした。
時代は明治維新(1868年)の直後で、1870年に施行された「刑法新律綱領」において「妾」という存在がしっかり「夫」「妻」に並ぶ身分として規定されていたのだそうです。
しかし、このとき妾は妻と全く同等の身分として規定されたわけではない。同じ二等親でも妻に準じる扱いだった。例えば、妾が夫と夫の親族に犯罪をなした場合は妻よりも一等重い刑罰が科せられたが、夫が妾に犯罪行為をした場合、妻に対するよりも数等軽い刑罰になった。
妾と愛人のフェミニズム 近 現代の一夫一婦の裏面史 石島亜由美著 青弓社 P.33
日本の戸籍制度のもととなる「壬申戸籍」は1872年から開始されるのですが、「妾」は翌年の1873年に追加されており、「妻ノ次」という身分で記載されることになります。
これにより、それまでは婚外子である未婚の母を持つ子どもは「私生児」として母親が一切の責任を持つことが基本で父親が認知した場合のみ「庶子」として相続権を持つことになったいたものが、父親の認知を必要とせず「妾」の産んだ子どもとして自動的に「庶子」になるようになりました。
さらには1876年には内務省の見解として庶子の男子は嫡出の女子に優先して相続の権利を得るというものまで出され、「妾」の産んだ子どもに対して非常に手厚い法的保護を(男性は女性に当然に優先されるという別の次元での差別はあるものの)与えていました。
ところが1880年になるとさらに新しい刑法が公布され(施行は1882年)、そのような手厚い「妾」の身分はあっさりと翻り、関連する条項が全て消滅してしまいます。
言い換えれば日本では当初は一夫多妻制を認める国家体制でスタートをしようとしていたものの、わずか10年程度でそれは消滅してしまったということになります。
ちなみにこの「妾」制度を消滅させる大きな要因になったのは1873年に設立された「明六社」という組織で、日本の近代化においてふさわしい姿とは何かを男性知識人たちが訴えたことによります。
明六社の近代的国家では「男女同権」による西洋的夫婦関係であるという主張は雑誌から新聞社、そして元老院まで及び、そこで「妾」制度なんて恥ずかしいものは法律で認めることはできない、という結論になったそうです。
フェミニズム系の議論では、「庇護される女性の立場を強化するべき」と「女性の自立を推進するべき」という相反する意見が対立しがちなものですが、この明治初期の妾論争の時期からもどの立場の「女性」を守るべきかでかなりねじれた議論がなされていたということがうかがえます。
この話の滑稽なところは、「妾」という身分は女性(正妻)の権利を侵害するけしからん存在であり近代国家の人権倫理にもとるものである、と言っておきつつも、妾の産んだ子どもも父親が認知しさえすれば庶子として相続権を得ることができるという決まりはそのまま残したということです。
女性の権利を守ると言っておきながら夫が婚外子を作ることは社会的には容認されており、法律はあくまでも西洋列強に対して「近代的国家である」というアピールのために使われていたというところが今も昔も政治家の考えることは同じだなあと思う点であったりします。
「妾」や「愛人」がという存在が憧れの対象に
「妾」「愛人」という言葉を聞いてすぐによいイメージを持つ人は少ないと思いますが、実際にはその位置づけは時代とともに変わってきているということも本書では解説されています。
一口に「妾・愛人」と言ってもそこから連想される女性のイメージは一つではなく、その時代でどういった人が主に選ばれたり自分からその身分を望んだりしたかが違ってきます。
創作物によく登場する「妾・愛人」のイメージと言えば、
- メイド、小間使、使用人など
- 芸妓や娼妓、その他バーのホステスなど水商売関係の人
- 会社の同僚や取引相手など仕事関係で出会う男性同様のキャリアがある人
- 元カノや元同級生など過去に関係があったが結婚に至らなかった人
といったところがざっくり挙げられるのではないかと思います。
これは時代により変遷してきた「妾・愛人」のイメージをそのまま並べたもので、小説やポップソングなどで描写されがちな人であると同時に、おそらくは多くの人が身の回りで聞いた不倫話で「そういえばそういう人がいたなあ」と思い当たるタイプではないかと思われます。
以下にそれぞれの特徴やどうして「妾」になるかや、どのような時代背景から生まれたかといったことを書籍を参考にしつつ私の意見も交えて説明していきます。
メイド、小間使、使用人
これは明治~大正、または昭和初期くらいの時代小説に登場しがちなタイプではないかと思います。
エロ漫画とかでも比較的このケースで「ご主人様」と関係を持っている女性は多く見かけるのではないでしょうか。
こういったタイプが「妾」になるのは2つのルートがあり、一つは使用人として就職したあとに主人に手を付けられるというケースで、もう一つは妾として抱えられると同時にその家に使える存在になるというケースです。
1つ目の最初は使用人として家に仕える場合、当時は未婚の若い女性は行儀見習いとして裕福な家庭に奉公に出るということが慣習としてあったため、そこで主人に気に入られてそのまま妾として家に残るということになります。
もう一つの妾が使用人になるケースですが、こちらは主人が妾にしたい女性を見つけたものの別宅をあてがうという選択をせずに家に住み込みにさせることから発生する関係です。
妾を囲っても妾宅は構えず、妻がいる本宅にともに同居させる場合もあった。妾宅を構えるが豪奢な妾囲いがあだになって経済的に逼迫し、妻の協力が得られず家政が荒れ、社会的非難を浴び、ついには身を滅ぼしていく。妻妾同居は、このような衰退の轍を踏まないための男たちの防衛方法でもあった。
妾と愛人のフェミニズム 近 現代の一夫一婦の裏面史 石島亜由美著 青弓社 P.64
妾を囲うことは男性にとっては自分の経済力を誇示するための一つのステータスとしての側面もあり、特に明治~昭和の成り上がり商人などの間では本宅よりも贅沢な家を妾に与えそこに通うということも多く見られていました。
しかし一方でその贅沢さが仇になり、事業が傾いたときに共倒れになるというケースもまた多く、そこから妾をいっそ妻や子どもと同居させるという方法もしばしば取られていたと言います。
今の感覚で言うと到底信じられない感覚かもしれませんが、むしろ外に出て自立した生活ができない立場の妻にしてみれば夫の女関係を自分の目の届く範囲内で管理をすることができるわけですし、家以外の場所に通い詰められるよりはと考えればいっそ妾が同居してくれた方が都合がよいという側面もあったわけです。
戦前の華族など血筋が重要になる人たちにとっては結婚相手は自分と同じ程度の身分の者を選ばなければならない一方でどうにかして男児を産ませなくてはならないという状況にいたため、もともと体の弱い華族の娘は「嫁ぐ」という義務を果たしたあとで出産は別の女性に任せる、というしくみも機能をしていたと言います。
この時代には夫から妻に一方的に離縁を告げることも可能な法律になっていたことから、たとえ心から納得をしているわけではなくても、自分が妻の座を奪われるくらいなら若い女性を妾として家に住まわせ自分の下においた方がだいぶまし、というふうになります。
妾はあくまでも「妻の次」という存在にとどまりますし、仮に妻が果たせなかった男児の出産をしたとしても、本妻と使用人という関係ができていれば妾が本妻になる足がかりにはなりません。
しかして家の中に女主人と使用人という二人(かそれ以上の)女性が同居する形が完成するわけで、この場合の「妾」は戸主である男性に対して性的な奉仕をすると同時に妻には使用人として下に見られ使われるようになるという形になります。
芸妓、娼妓、水商売関連の女性
一方その「妾」となる人を一体どこから探してくるのかということで言うと、今も昔もかなりの割合を占めるのが水商売関連の人です。
「芸妓」というのは花街(色街)のお座敷で歌や踊りで客をもてなす女性のことですが、ほとんどの場合がそのお座敷の奥にある寝室で夜の相手もしたとされています。
「娼妓」というのはさらに夜の相手の方が仕事のメインになっている人で、明治以降には「花街」と「遊郭」で芸妓と娼妓の職場を分離していました。
いずれにしても男の夜遊びとして金銭の対価として体を売る女性のことであり、そこから気に入った子を自分の妾として水揚げするという流れも妾になるというルートとして容易に想像できます。
この芸妓から妾になるということは花街界隈においては正規ルートとして認められており、「旦那」を見つけて身請けしてもらうことが芸妓の仕事から抜ける方法として確立されていました。
実際に伊藤博文、陸奥宗光、山縣有朋、桂太郎といった歴史上の人物も芸妓より妾を迎えていたりします。
裏返して考えれば、若くして芸妓や娼妓の世界に入った女性にとっては裕福な「旦那様」を見つけて仕事を抜けることはサクセスストーリーの一つであったと言えます。
現代のバーのホステスやデリヘル嬢、パパ活女子なども「愛人」として裕福な男性に囲われることがあるでしょうが、それがサクセスストーリーになるかどうかは少々変化をしてきているのではないかと思われます。
仕事を持つ自立をしたキャリア女性
妾や愛人というよりむしろ「不倫相手」として現代で多く選ばれるのがこのタイプではないかと思われます。
このタイプの「愛人」が多く登場するようになってきたのは1980年頃からで、好景気により女性が一人で暮らすのに十分な給与を得ることができるようになってきたことが影響しています。
しかし同時にこの時期は結婚した女性は婚前に仕事をしていても結婚後は自動的に専業主婦になるのが一般的な時代でもあり、女性の生き方として「専業主婦」か「キャリアウーマン」かという分岐が登場しはじめた時です。
男性にとっては結婚をして家に妻を閉じ込めておいて自分は外の世界でまた別の女性を物色するというスタイルができあがり、妻とはできない仕事の話をしながら豪華なホテルやレストランで恋愛を楽しむというバブリーな遊びがされるようになります。
妻の立場にしてみれば自分が家で家事や子育てを押し付けられる一方で夫は若くエネルギッシュな女性と恋愛を楽しむという屈辱的な立場になるものの、見て見ぬふりさえしていれば自分は「本妻」として庇護を受け続けることができるわけですから「亭主元気で留守がいい」よろしくある意味では黙認をしていた部分もあるでしょう。(そして場合によっては証拠を集めて相手女性から慰謝料をもぎ取ろうとしていたでしょう)。
逆に浮気相手となるキャリアウーマンにしてみれば、自分には十分な給与もあるし、わざわざ妻になって男のパンツを洗う立場になるくらいなら金を持っている遊び慣れた男性と割り切った関係をしていた方が楽という考えになります。
実際に90年代くらいにはわりと有名な小説家やポップシンガーが「愛人」という立場をモチーフにした作品を多く発表しており、そこには刹那的な関係に酔いつつも一抹の不安や寂しさを匂わせるような情緒を表現していたりします。
本書においては「男に尽くす役割を背負わされるくらいなら対等な立場で恋愛だけを楽しみたい」という考えで不倫をする愛人たちについて、現実では男社会の会社構造で上司たちの補助的仕事を担わされているという矛盾を指摘をしていたりもするのが面白いです。
妻という立場から見ればそうした楽しい恋愛という美味しいところだけを夫からかすめとっていく女性はクソ憎たらしい存在でしょうし、一方で愛人側の立場から見れば妻の座にあぐらをかいて家に閉じこもる女性はつまらない人間のように見えるでしょう。
個人的な見解でもありますが、現在も女性の社会進出が話題になったときに起こる女性同士の対立構造はこの頃の男を間に挟んだ間接的な憎しみ合いが少なからず関係しているのではないかと思ったりもします。
元カノや同級生など結婚せずにいた相手、その他
こちらは特に本書に詳細はなく私個人が「いそう」と思って挙げたタイプですが、ここ最近の浮気や不倫はこの手の人も多いのではないかという感じがします。
2000年代に入ってバブル期のような贅沢な恋愛は男女問わず一介のサラリーマンには難しくなってきました。
しかしながらそれで浮気や不倫がなくなるわけでもないのが「一夫多妻制」のひずみであって、どこかで相手を見つけようとするのが既婚者でしょう。
そうした意味で簡単にアクセスすることができる相手というのが元カノや同級生など出会いのきっかけがある人なわけで、他にも近所や子供関係で知り合った人とかも現代の不倫や浮気の相手になるんじゃないかと思います。
それともマッチングアプリで探すというのが一般的なのかな。
ただいずれもバブル期のように派手にホテルやレストランでデートを重ねるというよりも身近なところでささやかに恋愛欲を満たすような「愛人」がいまどきなのかなあという感じがします。
不倫や浮気というもの全般に対しての世間の目もSNSのため相当厳しくなってきており、妻の側も浮気が発覚したら即離婚という選択がしやすくなったこともあって、「愛人」という存在自体が過去と比較して欲望の規模が小さくなったみみっちいものになっているという印象もあります。
一夫一妻制のひずみと「結婚」の求める先
日本だけでなく世界的に採用されている一夫一妻制では「愛・性・結婚」を一体のものとするロマンティックラブイデオロギーという思想が前提になっています。
しかしながら過去の「妾」という存在は、結婚するということと子ども(男児)を生むということを別の人間に分業するために必要とされてきたものです。
日本において明治当初「妾」を法的に認めようとした背景には天皇制における世継ぎの問題があり、近代以前より女官制度という天皇に女性を側仕えさせて気に入られたら寝所に侍するという業務が当然に配置されていました。
※明治天皇の母親は女官の中山慶子であり、明治天皇の妻には子どもがなかったため女官との間に十五人の子どもをもうけており、そのうちの一人である柳原愛子が産んだ男児が大正天皇として即位をしています。大正天皇から一夫一妻制を採用しており、当時皇太子であった昭和天皇が女官制度を廃止しました。
それが時代の流れによって「愛・性・結婚」を一人の女性が担うことを当然とする常識が醸成されたわけですが、結果的に「性」のうちの「出産」部分だけが妻独自の役割とされ、「愛」の部分が外注されるようになるという不可思議な現実となっています。
日本において「恋愛」という言葉を広げた始祖は巌本善治と北村透谷とされていますが、北村透谷は著書において「恋愛は人世の秘鎗なり、恋愛ありて後人世あり、恋愛を抽き去りたらむには人生何の色味かあらむ」としており、恋愛をするのは人間の成熟に絶対必要なものであって生理現象として男女の性を求めるのは人間の価値を動物に落とすものだとまで言っています。
しかしながら「愛・性・結婚」のうち最も動物的であると言える出産の部分のみが「結婚」と一体化させられており、「恋愛」や「セックス」といったいわば恋愛の文化活動のような部分は婚外であるからこそ叶えられるという構図ができてきているのはなかなか興味深いというか、はっきり言って滑稽な現象です。
だからといって私自身、一夫一妻制をなくて一夫多妻制にするのが正しいことかというとそうとも思えませんし、仮にそうしようとどこかの政党が言い出しても世論は積極的に求めようとはしないでしょう。
答えのない問題ではあると思いますが、果たして「愛・性・結婚」を一体として扱う認識自体が今後継続可能なものなのだろうか?ということについてはもっと多くの人に考えてもらいたい問題ではあります。
まあぶっちゃけて言うと、ここまで愛人の歴史を辿ってみて思うのは「結婚制度における女性の立場の低さ」であり、根本的には明治時代の1898年から続く家族制度はクソみたいだなということなんですけどね。