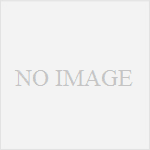「おふくろの味」という料理のジャンル

今回は読書感想文というよりは本の内容についての覚書のような感じになります。
紹介をするのは【「おふくろの味」幻想~誰が郷愁の味をつくったのか】(光文社 (2023/1/18)湯澤規子著)です。
「おふくろの味」というのはなんとなくみんな知ってるようなワードではありますが、具体的にそれがどういう料理を指しているのかということについては深く考えると非常に曖昧なものでもあります。
まず先に結論から本書の内容をかいつまんでまとめると、今メディアなどで使われている「おふくろの味」というのは源流をたどるとそれは「母親が作っていた料理の味」ですらない、フランス料理やイタリア料理のような特定の料理ジャンルの一つを示すものであるということです。
本書の帯にもあるように、なぜか「おふくろの味」の代表的な品目は「肉じゃが」のように扱われていますが、肉じゃがという料理が日本で一般的な家庭料理として扱われ初めたのは実は1975年頃の約50年前程度のことだといいます。
料理家であり、食文化研究家でもある魚柄仁之助は、「肉じゃがって、どこか懐かしいっていうか、おふくろの味的なお料理ですね」というようなコメントが料理本やメディアで登場するのは、一九八〇年代であったと指摘する。膨大な料理記事のデーターベースの中で「肉じゃが」の初出を探すと、最も古い記載は一九五〇年刊行の婦人雑誌『主婦と生活』一月号であった。しかし、これは家庭でつくるレシピではなく、食糧配給制度下での外食券食堂のメニューとしての登場であった。
「おふくろの味」幻想~誰が郷愁の味をつくったのか 光文社 (2023/1/18) 湯澤規子著 P.185
NHKの「きょうの料理」で初登場したのが一九六四年、その後約10年ほどの間に急激に「肉じゃが」という料理が全国に普及して、一般的に扱われるようになっていったというのが真相なのだそうです。
しかももともと「肉じゃが」はどこかの郷土料理というわけでもなく、居酒屋の一品料理として登場したものであったようですが、一九八〇年代になるといつの間にかこれを作れるかどうかが結婚相手にふさわしい女性が備えるべき料理レシピのように扱われるようになってしまいます。
身も蓋もないことを言えば、「肉じゃがを作れる女性は家庭的で家族を大切にする良妻である」ということ自体がメディアによって作られた一つの幻想であり、実際に肉じゃがを「家庭の味」と思っている人なんてほとんどいなかったということです。
そういえば、と思い返してもらいたいのですが、これを読んでいるあなたが男性でも女性でも自分の家庭でよく作られていた代表的な料理として「肉じゃが」の味を思い浮かべる人が何人いるだろうかということです。
肉じゃがという料理にこだわりを持って作っている人や、誰かに作られることに他の料理にはない特別の価値を感じている人は、そうしたメディアに浸りすぎて本当の自分の家庭の味を錯誤して記憶しているのではないかとすら言えます。
また本書においてそもそもとして「太古の昔から家を守る女が料理を作り、それを母から娘へと伝えてきた」ということ自体が大きな誤解であり、戦前までは普通に男性も料理を担当していたということをデータで示しています。
考えてみれば戦前までは現代のように便利な家電製品が揃っている時代ではなかったわけですし、野菜一つを漬物にするだけでもかなりの力が必要になります。
それに前回の「妾」の話でも少し触れましたが明治~戦前くらいまでは家庭内に小間使となる女性が同居する家庭も珍しくなく、家庭内の料理は妻ではなくそうした使用人たちが担当をしていたわけです。
使用人は女性ばかりではなく、時代劇などでまかないを女性だけが担当しているという描写自体が刷り込みによる間違いであるということにもなります。
ではその「おふくろの味」はどこから来たのかというと、新宿駅前の思い出横丁などに存在していた「地域名食堂」での提供料理であったと本書では紹介されています。
ざっくりと流れをまとめると、戦前までは先に紹介したように「料理=母の味」という認識自体が存在をしていなかったところ、戦後になるといわゆる「金の卵」として地方から集団就職をする人が増加します。
しかしそうして東京に出てきたばかりの地方出身の若者は十分に食べるものを買えるほどの余裕がなく、普段は配給の粗末なパンなどをかじるくらいしかありませんでした。
そんな食生活の乏しさと、離れて想うふるさとへの郷愁から、駅前にある「地方名+食堂」という場所に惹きつけられるようになります。
例えば「信濃屋」といった名前の店で「野沢菜」や「鯉こく」といった東京ではそうそう目にしない料理を提供していたというようなことで、そこから全国の地名系食堂は「金の卵」たちにとっての望郷の場所となっていくわけです。
そこに登場したのが肉じゃがのような一品料理であり、大衆食堂のメニューが望郷の念と組み合わさって「おふくろの味」という特殊な料理ジャンルができあがった、ということになるのだそうです。
「ふるさとの味」がいつの間にか「おふくろの味」という認識にすり替わったところも不思議なもので、そこには高度成長期からのジェンダーによる性的分業の意識も大きく関係しているのではないかと思われます。
同時に先程少し触れたような地方特有の郷土料理が近年どんどん作られなくなってきているということから、地域おこしとしてそうした料理を「おふくろの味」として宣伝目的で広げたということもまた一つの要因になっているとも紹介されています。
本書では、「幻想」が創られていくレシピやそれに関わる主体が幾重にも重なっていることを論じ、「おふくろの味」という概念をめぐって私たち自身が創り出してきた世界観がいかに多様で、移ろいやすく、様々な要素によって影響を受けて形成されているのかを明らかにしてきた。
「なんだ、そんなことか」と気づくだけで、私たちは他者や世界、そして自分に対して、少し寛容になれるのかもしれない。与えられたと思っていた世界観が実は、自分自身が創り出してきたものだと気づけば、未来の一皿を思い描くためのレシピはいつでも、いかようにもアレンジ可能なのだと諒解することができるのだから。
「おふくろの味」幻想~誰が郷愁の味をつくったのか 光文社 (2023/1/18) 湯澤規子著 P.267