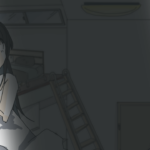第五章 運命の日まであと3日
午前中にバイトのシフトを入れたのは大正解だった。
早朝六時から交代する時間帯はやりたがる人も少ない狙い目のシフトではあるが、今日ほどそれを選んで良かったと思った日はない。
というのも午後からの予定を考えるとどうしてもソワソワ落ち着かない気分になっていたからで、もし自宅で過ごすことを選んでいたら居ても立ってもいられなくて無駄にどこかランニングにでも出てしまっていたかもしれない。
幸いにしてか土曜日の朝のコンビニは大繁盛でシフトの間の数時間ほぼ切れ目なくあれこれと仕事がわいて出ており、珍しく次のシフトの人に交代だと言われるまで終業時間に気が付かないくらいだった。
それでいい。あたしの場合、あれこれ先のことを余計に考えすぎるとだいたいよくないことが起こる。
*****
少し早めに待ち合わせの駅前に着いたが、あたしよりもさらに早く琥珀はそこで待っていた。
「あたしが間違えたか?」
「いえ。あなたは間違っていません。私もね」
駅前のシンボルになっている屋外ポール時計をわざとらしく見上げながらそう言うと、合わせるように琥珀は答えた。
休みの日に琥珀はあたしのバイト先のコンビニを訪れたことが何度かあったので私服を見たことがないわけではなかったが、それでもこうして改めて制服ではない姿で会ってみるとやはりその雰囲気の違いには戸惑う。
「模試が早く終わったのか?」
「どうしてですか?」
「いや、ちゃんと着替え直して出てきたみたいだから。時間に余裕があったのかなって」
あたしが普段コンビニ来る時よりも気持ち気合が入っている風の私服に気がついてそう尋ねると、琥珀はなぜか恥ずかしそうに顔をうつむかせる。
「凛、それを聞くのはマナー違反ですよ」
「えっ!あ、すまない。そう……なのか?」
そうです、といたずらっぽく琥珀は笑うと駅中の方へ歩き出した。
「行きましょう。せっかくのいいお天気ですし」
「そうだな。そういえば、今日の行き先について何か考えてきたか?」
「いくつかプランは考えたのですが……。凛はあまり人の多いところは好きではないですよね」
琥珀が見せてくれたのはいわゆる”デートスポット”をまとめた記事で、それで今更ながらあたしはこれから自分たちは「デート」をするのだということを実感した。
「まあな。テーマパークとかフェスイベントみたいなところは昔から苦手なんだ。それに今日は初めてあんたと二人で出かけるわけだし、あまりごちゃごちゃ考えることが多い場所より落ち着いて過ごせる場所がいいな」
言ってしまってからもし琥珀がそういった賑やかな場所が好きで期待していたらどうしようかと思ったが、口に出してしまっていたからもう遅い。
やっちまったかな、と思いつつ反応を伺ってみると琥珀は気分を害した様子もなく「それなら」と少し考えて私の手をとった。
「おすすめの場所があります。少し遠いですが、いいでしょうか」
「望むところだね。ところで、どこに向かうんだ?」
「今はまだ、ナイショです」
スルスルと駅前の人通りを器用に避けて琥珀はためらうことなく進んでいった。
あたしはその年上らしい頼もしさのあるリードとともに、ごくごく自然に手を繋いで歩いているということにも驚いた。
*****
楽しい時間は過ぎるのが早い、ということをもしかしたらあたしは生まれて初めて実感をしたかもしれなかった。
琥珀が案内をしてくれたのは電車で郊外方面に小一時間ほど向かった場所で、古い洋館や教会などの建物を見学することができる雰囲気のよい公園だった。
温室のバラ園や小動物とのふれあいスペースみたいなものもあって、まさに人混みを適度に避けたのんびり頭を使わないで過ごせるという要望にピッタリの場所と言える。
琥珀のエスコートも大したもので、明らかにこちらに気を使っているような卑屈さは微塵も感じられないのに、次はどこで何をするかということを嫌味なく提案してくれる。
こういう表現が適切かわからないが、ちゃんとあたしのことをゲストとして扱ってくれているのを感じる。
そうなのだ。あたしは今まで物心をついてから、他人からこういう風に丁寧な扱いを受けたことがまずほとんどなかった。
そのことを琥珀に正直に告げると、やや不安げな顔をしながら「余計なことでしたでしょうか?」と尋ねられた。
「そんなわけないだろ。ただ……なんだろうな。あんまりにも慣れなくてムズムズするんだ。あたしがいつものあたしらしくないっていうか」
「ふふ。今の凛は普段の凛でなければ何なんでしょうね」
「あんたといると、あたしは……。笑わないで聞いてくれるか?」
「はい、笑いませんよ。どうぞ」
「その、『女の子』になった気分になるんだ。ああ、やっぱり変だな、あたし」
「変でしょうか。私は別に」
「あーもういい。この話はおしまい。忘れてくれ」
「はい。忘れません、絶対に」
「おい!」
クスクスと笑い合う。
そうしているうちにも晴れた青空は夕闇の色が差し始めて、1日の終わりが近いことを教えてくれていた。
薄闇が迫る一瞬の光が過ぎて、名残惜しいがそろそろ魔法の時間は終わる。
電車に乗って帰り道を遡れば、また日常が戻ってきて、あたしの時間は動き出してしまうんだ。
「凛?どうか、しましたか」
公園施設を出て駅を直前にしたところで、あたしは夕日を背に立ち止まった。このまま大雨でも降って電車がなにかのトラブルで止まってしまえばいい、なんてことまで期待しそうになるがそんな気配は微塵もない。
運命は、何もしないでいて都合よく動いてくれるほどあたしに都合よくできてない。
「なんか、今日」
「はい」
琥珀は立ち止まったままあたしを待っている。
迫ってくる電車の時間にも急かそうともせず、辛抱強くあたしがこれから何を言い出すかをじっくり待っているんだ。
次の言葉は【あたしから】言い出すことに価値があるとわかっているように。
「帰りたく……ない、って言ったら。笑うか?」
ぎゅっと握りしめた拳に手が触れたのがわかった。
背中を押す夕日は正面に立つ琥珀の顔を赤く染めている。
「笑いません、が。笑顔になってしまうのは、許してくれますか?」
*****
「……うん。じゃ、火の元はちゃんとしてな。その子のお宅にはあとでちゃんとお礼しにいくから。……悪いな。キャンプ、楽しんできてな」
あたしが電話を切ってベランダから室内を見ると、ちょうど琥珀があたしの方を見て自分のスマホを指さしている。
何事かと急ぎ目にカラカラと大窓を開いて近づくと、保留状態にしたスマホの画面を差し出し気味に琥珀が急いで説明を加えた。
「宿泊をすることはOKをもらったんですけど、やっぱりどういう人と一緒か確認をとりたいみたいで。挨拶だけでいいので少し電話に出てもらえませんか?」
「ああ、わかった」
琥珀があたしの了解と同時に通話の保留を解除したので、それを受け取ってすぐさまバイトの接客モードに自分を入れ替えた。
「はい。唐沢凛と言います。琥珀先輩にはいつもお世話になっていて。すみません、急に。お勉強の邪魔はいたしませんので。はい、はい」
電話の先には母親かお世話をしているお手伝いさんか、言葉遣いが異様に上品な硬質な女性の声がした。
できる限りに相手に好印象を持たれるようにゆっくり落ち着いた返答をあたしがすると、相手は再び琥珀に変わってくれるようにと言ったのでスマホを返す。短く返答をしたところでわりとすぐに電話は切れた。
と、同時に琥珀がウインクをしながら指先でOKの形をつくる。
「うまくいったみたいだな」
「はい。電話を代わった時にはすごく喜んでいて。凛、さすがです」
「あたしだけに責任おっかぶせるなよ。あんただって」
「わかっています。『共犯』ですよね」
部屋は閑静な住宅街の一角にある堅牢な鉄筋コンクリート造のマンションにあった。
夕方のあたしの突然のわがままを受けて、琥珀は少し考えてすぐにどこかに連絡をとった。
電車に乗って戻っている途中で折り返しの連絡が来たようで、満面の笑みで「行き先を少し変更しましょう」と言ってきた。
「ダメ元で頼んでみたのですが。案外うまくいくものですね」
聞くと、このマンションは昔ピアノ教室でお世話になった先生の借りている部屋で、個人的にレッスンをする時や投稿用の演奏動画を撮影する時に使用している場所なんだという。
普段の生活はもっと都心に近い別の場所でしているのだそうで、今まで撮影の手伝いやら何やらで訪れたことはあったという。
ここしばらくあまり連絡をとってはいなかったが、思い切って「部屋を使わせてほしい」とお願いをしたら快く承諾をしてくれたということだ。
部屋を貸すついでに部屋の掃除やゴミ捨てなどをしてくれるようにと条件はついたものの、そのくらい全く何の問題もない。
あたしの方は妹のことが気がかりだったが、キャンプの出発は明後日の朝なので二泊くらい友達の家に泊めてもらえないかと電話をしたらむしろ喜ぶ感じでOKと言ってくれた。
そんなこんなで煩雑なあれこれを終えたところで時計を見たら、もうすっかり夜も更けた時間になっていた。
「なんか、急に力が抜けたな」
「大丈夫ですか?食事とか、外に出れます?」
少し考えたが、せっかく二人になれたこの空間でわざわざ外出しなおすのももったいない気がする。
「いや、冷蔵庫の中のものとか古くなりかけだけどなんかしら作れそうだし。簡単なものでいいなら用意できるから、琥珀、先にお風呂とか入ってきなよ」
琥珀はそれを聞いて一瞬ドキ、と動きを止めたように見えたが、すぐに「わかりました」とそそくさとLDKの部屋から洗面所の方に出ていった。
あたしはその背中を見送ってからゆっくりと腰を上げて人の家の冷蔵庫を開く。
勢いでこんなところに来てしまったが、どうしてだろう、この部屋に入ってからあたしは琥珀と指先にすら触れていない。