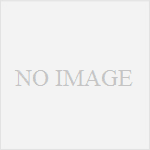※ツルさんとハチドリさんがまだペアになってない時のお話です。
隔離されてたハチドリさんをツルさんが身請けしたあとくらいの時間軸だと思ってください。
二次創作なので捏造あります。
随分長い間拘束されてきたせいだろう。
数歩先を歩いているツルについて行くハチドリは痛々しく痕が残っている自分の手首をペロペロと舐めた。
「少し休みましょうか?」
「ううん。それよりも早くハナシってのを聞きたい」
反抗的な態度により本来受けられるはずのケアを受けていないハチドリの体は医学の知識のない素人目にもわかるほどボロボロで、できる限りゆっくりと歩いているツルにもやっとついて来ているくらいだ。
それでもハチドリは全くそのことにつらさ見せる様子もなく、むしろ折れた自分の足のせいで速く歩くことができないことに苛立つ様子すらある。
ツルがハチドリを引き渡してもらうときに対応していたCAGEのスタッフから伝えられたのは、ハチドリには「無敵のギフト」が備わっているので身体的な痛みは感じないとのこと。
本来ギフトの存在は仮に仲間であってもおいそれと漏らさないものではあるが、例外的に早い段階で伝えられたのはつまり。
「……あなたを『痛み』で屈服させようとしても無駄、ということですね」
「なんか言った?」
「いえ。長く歩かせてしまってすみませんが、そこの丘を越えたところで休憩しましょう」
「わかった」
ゴールが決められて気持ちが切り替わったのか、ハチドリは瞳から不満の色を一瞬で消して無事な方の足を器用に使って大きくジャンプをした。
「あまり無理をするともう片方の足も折れてしまいますよ」
「平気!ムラサキも早く来なよ」
隔離室で対面してから既に何度も顔を合わせて自己紹介もしたはずなのに、ハチドリは一向にツルの名前を覚えようとはしなかった。
どう考えても「ツル」よりも「ムラサキ」の方が文字数が多いし覚えにくいような気がするが、効率とか生産性とかを気にする俗物的な思考はこの人にはないのだろうとツルは思った。
二人が向かったのはCAGE本部から離れた場所にある一応の安全地帯。
元々は都市部の片隅として中型のオフィスビルやマンションが立ち並んでいた場所だったが、今は見る影もなく瓦礫の山と化している。
とはいえ防衛エリアの内側にあるので、これから二人で話をしていて急に背後から魔獣に襲撃されるなんていう心配はない。
ツルは周辺でも比較的地面が平らになっている場所を選ぶと、ちょうどよく近くに転がっていたソファを2つ斜めの位置になるように置いた。
「どうぞ、お座りになってください」
「あんがと」
ハチドリがツルが指し示すよりも先にサイズが大きい方のソファに飛び乗るように座った。
スプリングが壊れていたソファはボフッと音を立てて大きな土煙が舞ったので、ツルは軽く手のひらで扇いで視界を確保すると隣に腰を下ろした。
「で?ハナシって何?」
深々とソファに体をうずめたハチドリはツルに切り出した。
隔離室で身動きできないように完全に拘束されていたハチドリをペアとして指定したツルが最初の条件としたのが「最初に話しておきたいことがありますのでついてきてください」ということだった。
大人しくハチドリがついてきたのはそうすれば自由になることができると言われたからで、実際この距離の移動中に全く文句を言うこともなかった。
最初の条件はクリア、というところでしょうか。と、ツルは思った。
しっかり愛用の武器を携えているツルに対して、ハチドリは怪我だらけの上に武器も没収されている。
私だったらこんな不平等で屈辱的な状況に素直に従うことができたでしょうか、とも思った。
「わざわざこんなところにお呼び立てしてすみません。CAGE司令部の中では少しやりにくい話でしたもので」
「アタシがムラサキとペアになるための確認をしたいってことでしょ。いいよ、なんでも試して」
「そこまでおわかりになっているのなら話が早くて助かります。実は私、少々CAGEの想定しているようなペアとは違った関係性を求めておりまして」
にっこり、とポーカーフェイスの笑顔を向けたツルに対してハチドリは特に何も感じていないように首を傾げた。
「あのさ、アタシってあんまり気の長い方じゃないんだよね。ズバッと何をすればいいのか言ってくれない?」
「それは大変失礼しました。では余計な雑談は省いて単刀直入に質問するとしましょう」
ツルは持っていた自分のメイン武器である杖を脇に置いて、懐から一丁の短銃を取り出した。
「ハチドリさん。あなたは自分のペアを殺すことができますか?」
そう言うのと同時にツルは持っていた銃をハチドリに向かって放り投げた。
パシっと鮮やかな手付きで受け取ったハチドリは、くるくると指先で武器を回してから中に弾丸が入っているかを確認した。
「意味がわかんないんだけど。あ、できるかできないかっていうことなら多分できると思うよ」
「随分とあっさりお返事をしますね。もう少し詳しく状況を説明しますと、そのペア相手が特別に憎いわけでもなく、どちらかと言えば好意的な感情を持っている場合であっても、ですよ」
「状況によるんじゃない?なんか前にも姐さんにめちゃくちゃ怒られたことあったし」
その話はツルも調べて知っていた。
確か初任務かそれに近いような頃にハチドリが一緒に出撃した仲間のことを気にせず暴れたせいであやうく貴重な戦力を大量に失うところだったと。
「では、その銃で私のことを撃ってみてください」
「はぁ?なんで?」
「特に理由はありません。かまいませんよ、本気で狙っていただいて」
ツルはまっすぐにハチドリの目を見据えた。
自分が本気であることを伝えるように。
実はツルはこれまで数回同じ【テスト】を別のトリに対して行ったことがあった。
その中には平時にはハチドリと似たようなやんちゃな性格をしたトリもいたし、戦場で落ち着いた指示を出すこともできていたトリもいた。
だけども誰一人として、実際に引き金を引くことができたトリはいなかった。
それではいけません。
そのような半端な正気を残しているような方では、私のペアはとてもとても。
もっと本当の、まがい物ではない真実の狂気を備えた方でなくては。
ツルがそんな過去に試されたトリたちの怯えた瞳を順に思い出していた時。
目前でキラリ、とまるで閃光が放たれたかのようにハチドリの瞳が輝き。
次の瞬間パン!と軽い音がしてツルの右耳の数センチ脇を一発の弾丸が通り過ぎた。
「なんだ、避けるんじゃん。ま、そうだと思ったけど」
「簡単に言いますね。これでもかなりギリギリでしたよ」
ハチドリの放った銃の軌道はまっすぐにツルの脳天の中心をめがけており、もしツルの反応がもう一瞬でも遅れていたらこのCAGEから遠く離れた人目のない瓦礫の山の中、致命傷を負って倒れてしまっていたことだろう。
「銃、返していただけます?」
「うん。どうせもう弾がないみたいだし」
もしツルがこれまでのトリ同様にハチドリがひるむと予想して銃に弾丸を多く装填していたら、おそらくハチドリはそれが尽きるまで追撃をしていただろう。
悪気なく銃を放り返すハチドリの顔を見てツルはCAGEに来て始めての悪寒をぞくりと感じていた。
「一つ聞いてもよろしいですか?」
「いいよー」
「もし本当に私が避けずに撃ち抜かれていたら、おそらくあなたは隔離室どころではないもっとおそろしい処遇を受けることになってたでしょう。そのことは考えたりしませんでしたか?」
ツルの質問にんー、と視線を上に向けてハチドリが少しの間考える。
「そうはなんないっしょ。アンタ、そういうヤツでもなさそうだし」
「呆れた。私を本気で殺すつもりで狙っておいて、さしたる根拠もなく大丈夫だと思っていたなんて」
「いいじゃん。大丈夫だったんだし」
その屈託のない態度にツルは思わずフッ、と吹き出してしまった。
こらえきれずアハハハ、と大きな声で笑い出すとハチドリはわけがわからないとういう怪訝そうな表情を向ける。
「アンタ、相当変わってんね」
「あなたに言われたくありません」
「そっかなー」
ひとしきり大笑いをして涙を拭うと、ツルはゆっくりソファから立ち上がりマントについた埃を払った。
「そろそろ戻りましょうか。ハチドリさん、あなたに必要なケアをすぐに受けられるように司令部に連絡をしておきます」
「やったー!あれ?て、ことは今日からアタシって……」
「どうかしましたか?」
「あのさ、アンタ。なんて名前だっけ」
「ツル、です。何度教えたと思ってるんですか」
「ツル。んじゃ、今日からアタシはあんたとペアってことでいい?」
「いいですよ。いい加減名前くらいは忘れないでくださいね」
「大丈夫。もう忘れないから」
傷ついた片足では壊れたソファからなかなか立ち上がれなかったハチドリにツルは手を差し伸べた。
先程見せた狂気や殺気はどこへやら、引き上げられるようにして立つハチドリはまるで子供のように無邪気で人懐こい顔を見せていた。
「こっからまた歩いて帰るの?」
「私におぶってもらいたいですか?」
「そうしてくれてもいいけど、なんか嫌そうだからいい」
そう言ってひょこひょこ、と飛びながらハチドリはここに来た道を戻りだした。
その数歩後ろでツルはゆっくりと歩いてついていく。
「ハチドリさん。さっきの銃弾のことですが」
「えー?何?」
「正直に言いますと、私。とてもとてもドキドキしました。高揚した、と言ってもいいかもしれません」
「コウヨウってどういう意味?」
ツルはバランスを崩しかけたハチドリのそばに歩み寄り、怪我をしている足の側から体を脇に差し入れた。
「これから起こることを色々と想像して、気持ちが抑えようもなく昂ぶってしまうこと、でしょうか」
「ふーん。よかったね」
間近で肩を貸しながら歩いていると、ハチドリの血と汗と、それからふわりと心地の良い匂いが感じられた。
「戻ったら、あなたにだけ打ち明けたいことがあります」
「わかった。よろしくね、ツル」
ドキドキする。
こんな気持ち、いつぶりでしょう。
ツルは自分の心臓が激しく鳴っていることに戸惑いすら覚えた。