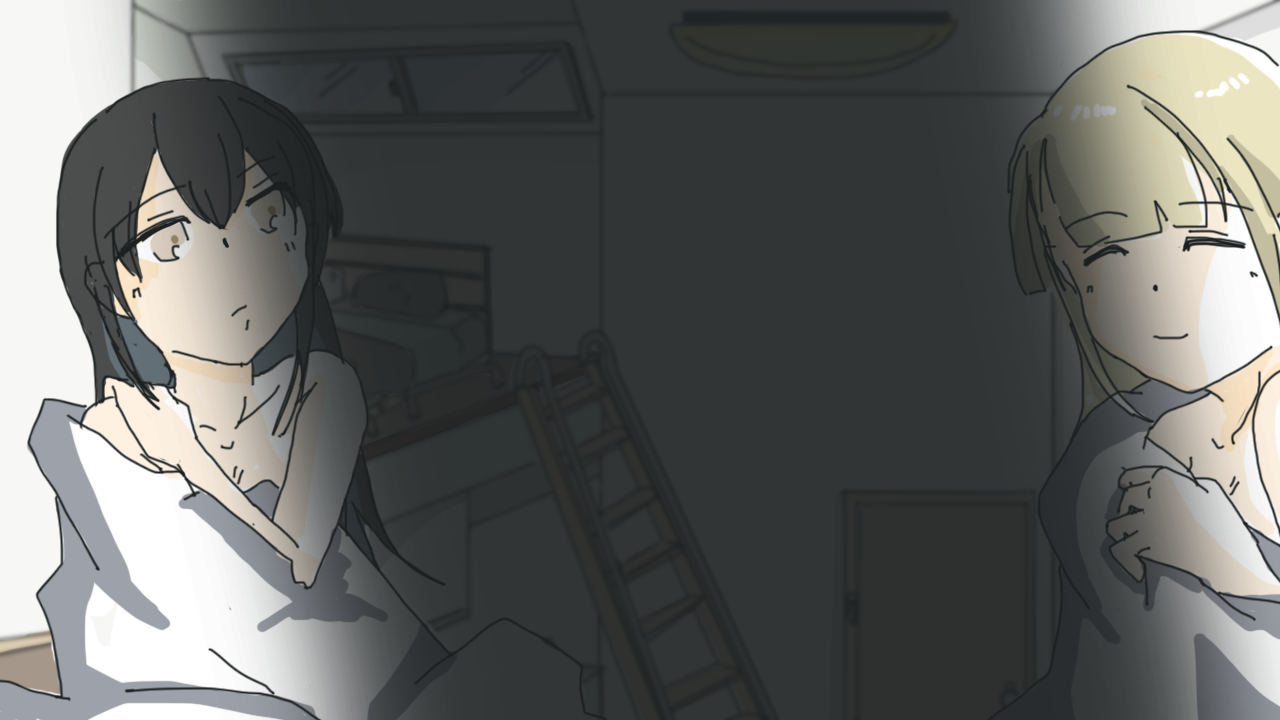第六章 運命の日まであと2日
正面の壁に掛かっていた時計が0時を回った。
真横のサイドテーブルに置かれた卓上ライトが白い壁をちょうど二分するように斜めに黒い影を作っていて、暗闇に包み込まれようとしているこの部屋で儚い抵抗をしているようにも見える。
「凛、もう眠ってしまいましたか?」
「いや、まだだ」
この質問ももう三度目くらいになるだろうか。
突然押しかけることになったこの部屋は1LDKの間取りで、リビング部分に小さめのロフトがついている。
もともとピアノレッスンと演奏撮影用に借りている部屋ということもあり、防音室には個人所有としてはかなり立派なピアノと撮影用の機材が置かれていた。
一方で生活の場所としてはそれほど重要視はされていないようで寝室としての家具が置かれているのは狭めのロフトの上であり、しかも質素なスノコの上にマットが置かれただけのシングルベッドが一つとなっていた。
もちろん好意で利用をさせてもらう立場なので全く文句を言う筋合いもないわけだし、あたしからすれば自宅のせんべい布団に比べればこちらの方が上等ですらある。
食事や入浴などをお互い済ませた時にはもう遅い時間になっていたので、テレビなんか見てゆっくりくつろぐようなこともなくほぼそのままこの狭いベッドルームに直行することになった。
急な泊まりでパジャマなんて持って来ているわけもなく、ほぼ下着同然の姿(というか実際に下着)で寒さをしのぐようにベッドの中に入り込み。
入り込み。
そのままお互いの体温を感じることができる微妙なギリギリの距離でまんじりともせず時間だけが過ぎている。
この状況は完全にやり直し前の一週間で発生してはいないもので、全ての言動に見本はなくたった今この瞬間の判断に頼らないといけない。
今更だが、このまま眠って朝を迎えるという選択も残されている。
しかし残念なことに昨日早番でバイトをしていたにもかかわらずあたしはちっとも眠くなく、琥珀もさっきから落ち着かなく少しずつ寝返りをうっている。
別にためらう理由もないはずなのにどうしても自分から動く勇気が出ない。
「琥珀、あのさ」
「何ですか?凛」
「今日、楽しかったな。すごく」
ああ、また間違えた。今日、ではなくもうあれは昨日。
過ぎてしまった貴重な一週間の中の1日。
「あの……凛」
「何だ?」
「一つ、気になっていたことがあるのですが。聞いてもいいでしょうか」
沈み込んだ空気を壊さないようにか、ほとんどささやくような声で琥珀が言った。真剣味を帯びた口調に反射的に身構えてしまう。
「凛は、何か気にしていることがあるんでしょうか?その、私といるときに」
ぎく、と一瞬肩がビクつきそうになるが深読みしすぎかと思い直して一つ深呼吸をする。
「そんなつもりはなかったが。琥珀からはそんなふうに見えたか?」
「いえ、違うならいいんです。ただ、ほんの少しだけ、時々ですが、何か凛は私の知らないことを気にしているように思えることがあるので」
「そりゃまあ、あたしはあんたにあたしの悩みの全部を話してるわけじゃないからな。あんただってそうだろ?」
できるだけ明るく茶化そうとしてそう言うと、直後にドン、と肩口に何かがぶつかってきた。
そっと顔を傾けると、自分の二の腕近くに琥珀の額がくっついていることがわかった。
そして次にぎゅっと仰向けになっているあたしの左手を両手で包み込むように握り込まれる。
布団の中で生ぬるい空気が充満しているところ、するりと指先が絡み付けられるのを感じて瞬発的に体温が上がった。少し考えて、こちらからも握り返して体を琥珀の方に向けた。
額に掛かった前髪を指先でかき分けるとくすぐったそうに目を細めた琥珀と正面から見つめ合う形になる。
「あたしみたいなやつが何を言っても説得力がないかもしれないけどな。一つ、信じてほしいんだ」
「凛……」
「あたしがもし何かに悩んでいたり、あんたに隠し事をしているように見えたとしても。それはあんたを軽く見ているとか信用してないとかじゃない。あたしなりに、言うべきじゃないって考えてそうしてることなんだ」
そもそもあたしは上手に嘘をついて人を欺くことができる器用な人間じゃないしな。
言葉で反論をしようか考えあぐねているようにまっすぐにあたしを見据える琥珀に軽く額をつける。
「でも、さっきみたいにどうしても気になってしまうことなら遠慮なく言ってくれ。あたしはあんたみたいに上手に察して相手を気持ちよくさせるスキルはほぼゼロだからな」
「その言い方は……凛、私のこと何だと思ってるんですか」
むくれた琥珀を笑ってあたしはまた少し肌の距離を近づける。自然と声色が落ちて囁きあう。
「いい子で、きれいなお姉さん、かな」
「凛。キスしてもいいですか」
いいよ、と最後まで言うよりも先に唇が重ねられた。
少しずつ荒くなっていく吐息の途中であたしがサイドテーブルのランプに手を伸ばそうとしたところで琥珀がその手をつかんだ。
「消さないでください」
「そうか、あんたがそう言うならいいよ」
「ありがとうございます」
あたしは琥珀みたいにもてなし上手というわけじゃない。
だけどもこうして琥珀が喜んでくれることを探せたことを喜んでいる自分がいる。
琥珀はあたしのすることに対しての「嬉しい」のハードルが低いとは思うけれども、それでもあたしの不器用な仕草でも素直に喜んでくれているのはあたしにとっても大きな幸せだと思った。
*****
少しだけ眠って、それから部屋の掃除を一緒にして部屋を出たのはもう夕方近くだった。
名残惜しい気持ちがないわけでもなかったが、永遠に時間が続いていくわけではない。
それに、琥珀とはもうこれまでの距離感ではない。
昨日の出発点でもあった駅前に戻ってきたところで少し歩くといつもの帰り道に入った。
いよいよお互いの家路に分かれるところで琥珀があたしの袖をつかんで引き止めるようにする。あたしは駄々っ子をなだめる気分でその手を軽くつかんだ。
「また明日。学校で会えるだろう?」
「それはそうですけど。凛は平気なんですか」
「まあね。あたしは色々とすることがたくさんあるから」
そうでもして無理に現実のことを考えようとしなければあたしはいつまでもここにとどまってしまう気がした。
「凛の家は、ここからすぐ近くなんですよね」
ドキ、とあたしの作っていたヘラヘラ笑いが消えた。
「ああ、そう……だけど、それが?」
「いえ、近いのであればお家まで送って行きたいなって」
これは重大な選択肢だと思った。なんで気が付かなかったんだ、とあたしはここで自分の間抜けさを実感する。
「それは、やめておいてくれないか」
「何か、都合が悪いんですか?」
「ひどいボロ屋だし、あんたが見ても面白いものは何もないよ」
「そんな。凛、何か変です。私に家に来てほしくない理由があるんでしょうか」
ある、とは言えない。あるんだけど。
このまま運命が変わらなければ、2日後にあたしたちはクソ親父を殺してしまうことになる。
だけどももし琥珀があたしの家を知らなければ、あたしがクソ親父と何かもめてもその現場に琥珀が訪れることはない。
そう、そこさえ防いでおけば簡単に変えられる運命だったんじゃないか。
あたしは琥珀の両肩をぐっとつかんでできるだけ真剣な目を向けた。
「琥珀、約束してほしいんだ」
「はい。何でしょう」
「お願いだから、あたしの家について詮索をするのはやめてほしい。それは琥珀が何か誤解したくなるようなことがあるからじゃなくて、そうしないといけない事情があたしにあるからだ」
まだ納得できないような顔をしているけれども、まさかあたしが今懸念していることをそのまま話すわけにはいかない。
「来てほしい時には、あたしの方からあんたを呼ぶ。だからお願いだ」
そう言うと琥珀はうなずいた。
「わかりました。では、そうします」
ありがとう、と言ってあたしは琥珀の手を離した。
琥珀はあたしに嘘をつかない。
だから多分これで、何か大きな変化が起こってくれるはずだ。
*****
あたしが家に帰って来た時、しん、と無人の静寂だけがそこにあった。
妹に連絡をとってみると、今日は朝から友達の家に出かけていて今はそのお宅で一緒に過ごしているのだという。学校のキャンプは明日の朝に出発になるからそのまま直接学校に行くということだった。
明るそうなメッセージの様子にあたしは安心をして、明日から気をつけて、と保護者らしい注意喚起をしておいた。
室内を明るくしてよく見回すと、テーブルの上に汚らしい灰皿と散らばった吸い殻があった。よくよく注意をして部屋の匂いを嗅いでみるとうっすらと最近吸ったのだろうタバコ臭も残っている。
あたしは寒さをこらえて部屋の換気をしつつ、クソ親父がどの時間帯かにこの家に戻ってきた痕跡を消すための作業をした。