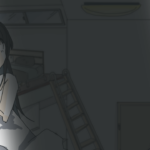第七章 運命の日まであと1日
月曜日。運命の日まであと1日という日。
事件が起きたのは午前中の、昼休みまであとわずかという時間帯だった。
正直あたしは油断をしていた。
昨日までの6日があまりにも心地よくて、順調で。だからもしかしたらこのまま静かになるように任せていれば勝手に運命は良い方向に向かっていってくれるものなんだろうって少し思ってしまっていた。
授業中に突然教室の扉が開き、学校事務の職員さんが急用だとあたしのことを呼び出した。
そこで話を聞いてすぐにあたしは荷物をまとめて学校を飛び出した。行き先は市内にある大きな病院だった。
到着をするとすぐに病室の中に通された。
白くのっぺりとした壁に囲まれたベッドの上に妹は横になっていて、痛々しく頭に包帯が巻かれている。
「一体……何があったんですか?キャンプに出かけたはずじゃ?」
妹を前日に泊めてくれた友達とその保護者の方のお話では、今朝は予定通りに起きて支度をし二人で学校に向かったのだという。
キャンプの参加者は学校前に集合し、そこから現地に向かうバスに乗り込むことになっていた。
妹とその友達がそうして校門前に一緒に並んで待っていたところ、突然そこに一人の中年男性が話しかけてきた。
クソ親父だ。
その男性の容貌や言動の説明を少し受けただけであたしはそれを確信した。
昨晩は結局一度戻ってきた気配こそあったものの、クソ親父がアパートに来ることはなかった。
考えてみればこの一週間ほぼ姿を見ていなかったわけなので、都合がよいといえばそうだがどこで何をしていたか全く気にしていなかったのは痛い落ち度だったと思う。
生徒たちの中に不似合いに近づいてきた中年男は妹を見つけるとまっすぐに近づいてきて、小遣いを持っていないかと聞いてきたという。
実は以前にあたしが何かあったときのためにと自宅の押入れの隅にこっそりと隠していたへそくりがクソ親父に見つかり、黙って持ち出されてしまったということがあった。
それがわかってから隠し場所をもっとわかりにくいところへと変えるようにしていたのだが、今回妹のキャンプ費用とその小遣いにといつもより多めに渡していたのだった。
妹の友達の話では、クソ親父は「お前が金を持っていったんだろう」とか「子供が贅沢するな」とか、あとは「今どうしても必要なんだよ」とまるで懇願するかのような言い方でしつこく食い下がってきたという。
学校のキャンプについては以前から自宅で話をしていたし、細かい日程については学校から配布されたプリント用紙を冷蔵庫前に貼り付けてあったのでそこから居場所を見つけるのは全く難しいことではない。それでなくともあたしたちが持っている金については異様に鋭い嗅覚を持っている最低なクソ野郎だった。
妹は突然の来襲に驚きながらも周囲の目の恥ずかしさに激しく抵抗をし、絶対に財布を出そうとはしなかった。
あたしが知っている限りでは、妹はあたしと違ってそんなに気が強いタイプではないので父親に金をせびられたりしたときには無駄な抵抗をするよりも大人しく渡してその場を諫めようとすることが多かった。
だから妹の友達のその証言はあたしにとっては意外だったし、きっと思うところがあったんだろうと感じた。
だけどそんな態度がクソ野郎の気に障ったのだろう。
しばらくもみ合いになった挙げ句にクソ野郎は妹に手をあげ、それでバランスを崩した妹が吹き飛ばされる勢いで歩道脇の花壇に頭をぶつけてしまったという。
鈍い音がして妹の友達が駆け寄ると、妹は反応がなくその場でぐったりとしてしまった。
クソ親父は「俺のせいじゃねえ」とか言いながらも妹の荷物を探ろうとしていたが、さすがに周囲に人が集まってきたせいか諦めて逃げ出して行ったらしい。
その後はかなり混乱を極めたようだったが、素早く担任の先生が救急車を呼び、妹の友達などの話からあたしのところに連絡が来た。
*****
外来の時間が終わり、ガランとした病院の待合室の椅子に座ってあたしは考えていた。
うつむいて自分の組んだ手を見つめていると、力を入れすぎていたせいで血流が止まり白くなっていることに気がついた。
「凛、ここにいたんですか。大丈夫ですか?」
今日の昼休みには琥珀と一緒に過ごす約束をしていたので、かなり遅くなってはしまったがだいたいの事情はメッセージで連絡をしていた。
学校が終わったあとで自分もお見舞いに行きたいがいいか、と返信が来ていたので少し迷って「あんたがそうしたいなら」と返しておいた。
静かな病院の待合室は壁にはめ込みのステンドグラスが飾られている。
平和な空をたくさんの鳥達が羽ばたいていく図柄だ。
病院内で診察を待つ患者さんたちのストレスを少しでも鎮めようという意図でつけられているのだろうけども、残念ながらそのくらいのことではあたしの気持ちを落ち着かせることなんてできそうもない。
「妹さんのご容体は?」
「ああ。今は落ち着いたみたいで眠ってるよ。さっき、少しだけど意識が戻って話もできたんだ」
そうですか、と琥珀は言ってあたしの隣に座った。「良かったですね」と軽々に言わないところも琥珀らしい。
あたしが次に何を言うかじっと待つ琥珀を傍らに感じていると、ぶるぶると体が止めようもなく震え始めた。
「……妹が」
「はい」
「『お姉ちゃん、ごめんね』って。あたしに」
「……はい」
「あたしのせいで、あんなことになったのに。あたしのせいで!」
琥珀が強く握りしめていたあたしの手の上に手を重ねた。ガタガタ震えがと落ち着かなかった体がゆっくりと収まっていく。
「あなたのせいではありませんよ、凛。あなたは妹さんのために最善を尽くしたじゃないですか」
「だって、こんなこと。起こらないはずだったんだ!前には、妹には何も」
「しっかりしてください!凛」
ぐっとあたしの手を握る手に力が込められて、あたしは琥珀の方へと顔を向けた。
琥珀は真剣に、鋭い視線をあたしに向けている。普段はどんなことがあっても温和な琥珀がこんな表情をするのを今まで見たことがない。
「あなたが今自分を責めても物事は何も好転しません。妹さんが大変なときにあなたが後ろ向きになってどうするんですか」
正論だ。あたしは確かに弱気になってしまっていた。自分のせいで何もかもが起こっていると思い込んで。
やり直し前の一週間ではなかった琥珀とのことが妹の怪我の遠因になってしまったという可能性は十分ある。だけどもだからといって何もせずにただ一週間が過ぎるのを待っていることが正しかったかと言われるとそうではないはず。
琥珀を選んだことで起こった不幸をその選択のせいにするということは、琥珀のことを否定しているにも等しい。それは絶対に違う。
「あんたの言う通りだな。琥珀」
「凛」
あたしは今、自分の運命を変えるためにここにいるんだ。後ろ向きになっている暇なんてない。
「今日はこれからどうするんですか?」
「まだ妹の容体が安定しないからな。今夜は付き添いをしてここに泊まろうと思う」
「何か手伝えることはありますか?」
「ああ、すまない。今色々とやらなければいけないことがあるんだった」
あたしはやっとそれまで座っているだけだった腰を上げることができた。琥珀がそれを追って立ち上がったときに、ふと思いついてぎゅっと強く抱きしめた。
「琥珀。よく聞いてほしい」
「はい」
「これから何が起こっても、あたしのことを信じてほしいんだ」
「凛?どういう意味ですか?」
あたしの背中に琥珀の手が添えられたのを感じる。
「あたしはやるべきことをする。自分の【運命】を変えるために」
ぎゅっとあたしの制服の背中を琥珀の手のひらが握りしめた。がらんどうの待合室の静けさの中に、琥珀の返事が妙に大きく響いた気がした。
「凛。私もあなたの【運命】に、ともに居させてください」
*****
夜遅く、妹が眠っているベッドの脇でうとうとしかけていたあたしのところにメッセージが入った。
心配性の琥珀がまた何か言ってきたのかと思ってあたしがかすかに笑顔になりながらスマホを取り出すと、その画面に表示された文字に一瞬で顔が強張った。
送信元はクソ親父からで「いつ戻る」とあった。
あたしはスマホを投げつけたい衝動にかられながらもできるだけ冷静にどこにいるかを尋ねた。当然とも言えるがそれに真面目な答えは返ってなんてこない。
凛:クソ親父。あんたのしたことは立派な傷害罪だ。あたしが警察に届け出ればあんたはムショ行きになるんじゃないか。
それに対しての返答は嘲笑的で、あたしを挑発するような口調のものだった。「やってみろ」と。
クソ親父:別に構わんよ。ただお前らは未成年だからな。うまく二人一緒の施設に入れてもらえればいいな。
あいつはあたしの弱みが何なのかを十分にわかっている。
そしてバカなりにどうすれば自分が巧妙に罪を免れることができるかということも。
クソ親父:お前も苦労していい高校に入れたのに、犯罪者が身内にいるんじゃどうなるかわかんねえな。せめて卒業してからの方がちったあマシな仕事に就けるんじゃねえのか?
凛:クソ親父。何が目的だ。
金だ。
そんなの聞く前からわかっている。
クソ親父:俺さあ、明日までに払わねえとマジでやばいことになる金があんだよ。どうせお前のことなんだからどっかに隠してんだろ。
そんなことだろうと思った。
あたしは思っていることを押し殺して表情のない顔のまま次のメッセージを打ち込む。
凛:明日、アパートに来い。
ふざけたような笑顔のスタンプがクソ親父から送られてくる。
クソ親父:いいねえ。凛ちゃんはいい子だ。生かしておいた価値があった。
価値。あたしの、生きている価値。
それ以上会話をするのも我慢ならなかったのであたしはそこでスマホを置いて電源を切った。
点滴を腕に差したままの妹は、ベッドの上ですやすやと寝息を立てている。
あたしは自分の手を握ってそこにかすかにでも残っているかもしれないぬくもりを探した。
暖房はしっかりついているはずの部屋なのに、指先はものすごく冷えていて気を抜いたら全身が震えだしそうな気がした。
「琥珀……」
しんしんと冷気が窓際から伝わってきて、明日あたりから雪が降り出しそうだった。